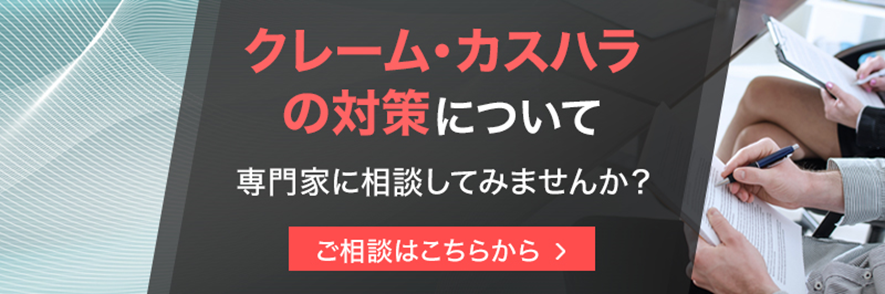ビラ撒きや怪文書など嫌がらせの伴うカスハラは、組織での対策が有効
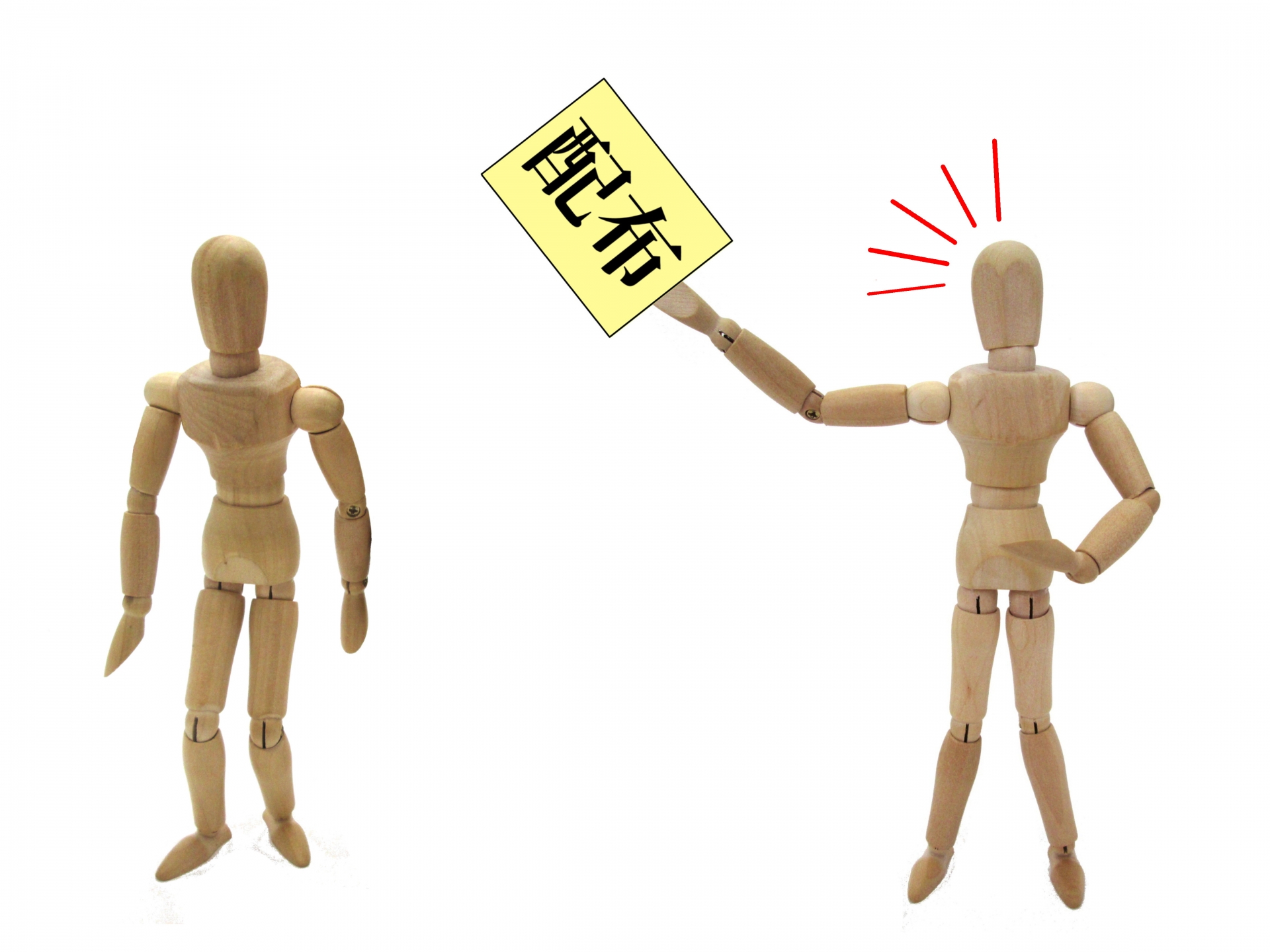
近年、「カスハラ(カスタマーハラスメント)」という言葉が一般的になったことで、企業側でも対策が進み、明らかに不当な迷惑行為なら、例え相手がお客様だったとしても「毅然と対応する」という方針が共有されるようになって来ました。
しかし、毅然と対応したことでその場は治まったとしても、それでそのクレーム自体が終息したかと言うと、そうでは無い場合もあります。ある美容室では、カラーリングを間違えたことによるクレームに対して、店長が、「あまりしつこいと警察を呼びますよ!」と強く言ったところ、お客様はその場では帰って行きましたが、その後、店外のラックや駐車中の車などにそのお店を批判するビラや怪文書を入れられるようになったケースがありました。
そのお店の場合、元々はカラーリングを間違えた美容師や、事情を確認せず追い返すような対応をした店長の方に原因があったと思います。しかし、ビラや怪文書の内容は、個人情報や猥褻な内容を含むその美容師への誹謗中傷であり、原因と無関係なものであり、非常に大きな恐怖・ストレスとなっていました。
そこで本コラムでは、部下の分も合わせると3,000件以上のクレームに対応して来た元・コールセンターの品質管理チームマネージャーであり、中小企業診断士でもある筆者が、ビラ撒きや怪文書などの嫌がらせをされたときの対応について解説します。
なぜ今、サービス業のカスハラ対策が必要か? 事例に学ぶ5つの対策
ビラ撒きや怪文書など嫌がらせの伴うカスハラは、組織での対策が有効
カスハラでは、現場での初動対応策が重要
冒頭の例のように、従業員個人に対し具体的な嫌がらせ行為をしているような場合には、そのまま放置しておくといつエスカレートして更なる危害に及ぶか分かりません。そのため、従業員の安心・安全の確保を最優先に対応することが大原則です。例え自社に何らかの落ち度があったとしても、それは社内で必要な叱責や教育を受け、しっかりと反省すれば良い話しであり、このような嫌がらせ・誹謗中傷を受け入れる必要は全くありません。
「当社にも原因があったし」や「もう少し様子を見てみよう」などと軽視せず、速やかに以下のような対応をすることを強くお勧めします。
嫌がらせ被害に遭っている従業員を避難させる
できれば、事態が落ち着くまでは配置転換で別店舗業務やバックオフィス業務をしてもらったり、実家など普段と別な住所から通ってもらったり、といった対策を検討します。可能なら、在宅ワークにしたり有給消化をしてもらっても良いでしょう。「被害者がそんな不便なことをするのはおかしい」といった意見もあり、確かにそうかもしれませんが、筆者は、目の前の危険回避が最優先であると考えます。
施設管理者として、クレーマーに退去や立ち入りお断りを要請する
嫌がらせの相手が特定できている場合は、施設管理者から、退去要請や立ち入りお断りの要請をします。意図が明確に伝わり、記録にも残りやすいように、文書での要請がお勧めです。
相手が特定できていない場合でも、後述のような警告表示で嫌がらせを牽制しましょう。
ビラや怪文書そのもの、監視カメラの映像など、嫌がらせの証拠の記録を保存する
警察に相談する場合は、相談する内容を裏付ける証拠が重要です。ビラや怪文書の内容は、名誉棄損罪や侮辱罪に関わる重要な要素なので、投函日時が分かるように整理して保管しましょう。また、監視カメラなどを設置している場合は、訪問(侵入)の回数や、そこでの言動なども、被害状況を示す重要な証拠です。監視カメラのデータ保存量が決まっている場合は、その量を超えて上書きされてしまう前に、必ず証拠として保管しておくようにしましょう。
自社のクレーム・カスハラ対応を記録する
自社の対応は、損害賠償請求を考える場合の重要な情報です。例えば退去要請についてなら、いつ、どういった状況下で、誰が、どんな内容で(文書があればその文書を保管)、誰に伝え、相手はどう答えたか、仕事に対してはどのような影響があったかといったことを記録しましょう。
なお、記録については、具体的な迷惑行為が起きた後に対応するのは当然ですが、よりしっかりと対策を講じて行くのであれば、平時からクレームの種を軽視せずちゃんと報告するように教育し、対応マニュアルの中にも対応記録や証拠の保全を盛り込むなど、有事の際に使える情報が自然に記録されるように組織的な仕組み作りをして行きましょう。上記のような仕組みが機能すれば、クレームやカスハラの削減だけでなく、顧客満足度の向上にも活用が可能です。
従業員の安心・安全が脅かされる場合には、躊躇せず警察の助けを借りる
従業員個人が標的となっている場合、施設内への無断侵入や無許可での投函などを行っている場合、業務の縮小など具体的な実害が出ている場合、その他、従業員の安心・安全が脅かされていると判断した場合には、前述のような初動対応と並行して警察に相談をします。
刑法違反としての対応の枠組み(名誉棄損罪、侮辱罪、業務妨害罪など)
録画映像など嫌がらせの証拠がある場合は、刑法違反が認められる可能性があるので、被害届や刑事告訴とともに警察に提出します。
犯人が分からない場合や証拠が無い場合でも、実際に嫌がらせをされのであれば、警察に相談してみましょう。警察であれば、我々一般市民が見れないような防犯カメラの映像を見れる場合もあるので、犯人や証拠が特定できる可能性もあります。何より、こちらが躊躇している間に、更に酷い嫌がらせや、最悪の場合には暴力行為などに発展する可能性もあるので、そうならないためにも速やかに警察へ相談しましょう。
刑法違反に該当するか否か判断できない場合は、「#9110」や所轄警察署に相談する
ビラや怪文書など嫌がらせの内容が犯罪に該当するのか判断しかねる場合には、まずは#9110(警察相談専用電話)への電話相談をするのが一法です。ただし、個別具体的なアドバイスや、今後嫌がらせがヒートアップした時に速やかに事件化してもらいたい場合には、その時点で確保している証拠や経緯説明書などを所轄警察署の生活安全課に持って行き、標的となっている従業員とともに企業側の責任者から直接相談しましょう。
【保存版】カスハラへの警察相談・被害届の出し方ガイド|企業の対応実務
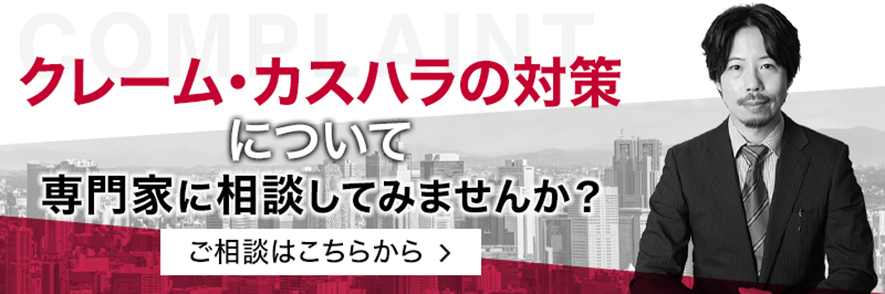
社内体制の整備と、従業員の心身のケアが重要
ビラ撒きや怪文書などの嫌がらせをされると、その従業員本人にとっては非常に大きな恐怖ですし、他の従業員にとっても迷惑感や不快感は甚大です。そういった心理状況に対し、企業が適切に対応できなければ、最悪の場合、嫌がらせの相手と直接接触して別な揉め事になってしまったり、といったことになりかねません。
そのため、例えその嫌がらせ行為が自社に全く非が無い理不尽な行為であったとしても、企業としての姿勢を明確に打ち出し、従業員を守ることが不可欠です。
従業員への経緯説明と、経営の「従業員を悪質クレームやカスハラから守る」という強い意思表示
嫌がらせは、本人にとって恐怖であるとともに、他の従業員にとっても大きなストレスです。
ただ、筆者の経験上、それ以上にストレスが大きいのは、嫌がらせや誹謗中傷を受けている状況下で、会社がちゃんと説明したり従業員を守る姿勢を見せないことにより、「こんなに大変な思いをしながら嫌がらせを我慢しているのに、会社が助けてくれないなら、、、」と思わせてしまうことです。
上記のように思わせてしまわないためにも、事業責任者や経営者の口から経緯をちゃんと説明するとともに、「従業員の安心・安全は、組織として断固守る!」という強い意思表示をすることが重要です。
ビラ撒きや怪文書への遭遇時や話しかけられた時などの行動の共有
細かいようでも、実施に遭遇した時の対応をセリフや動作のレベルで具体的に共有しておかなければ、最悪の場合、捕まえようとこちらから近づいたり、挑発するような言動をしたりして(自招行為)、別な揉め事になりかねません。そのようなことにならないように、「見付けても近づかず即通報」「話しかけられたらビラや怪文書は受け取るが一切答えず上司に報告」など、シチュエーションに応じたリアクションを共有します。
相談窓口と、継続的なモニタリング・メンタルフォロー
警察への通報や弁護士を通じた仮処分の申し立てをしたからといって、即相手が逮捕されたり、その場で嫌がらせ行為が止まるとは限りません。数か月かかることも珍しくないので、その間の嫌がらせ対策は不可欠です。また、既に起きてしまった嫌がらせによる従業員の心理的ダメージは、例え相手が逮捕されたとしても、無くなる訳ではありません。そのため、被害拡大を防ぐための業務上の対策とともに、現場の従業員がいつでもどんなことでも相談できるような相談窓口を作り、窓口を作るだけでなく定期的な1on1などによりモニタリングを行い、メンタル不調が無いかフォローして行きましょう。
なお、メンタルのフォローについては、必要に応じ、産業医や外部の臨床心理士などの専門家に参加してもらうことも重要です。
カスハラが発生したら? | 退職を防ぐ、組織的対策の6つのポイント
ピクト掲出(警告表示)などによる注意喚起
例えば、敷地内や建物内に「敷地内への無断立入り禁止」や「無断でのビラ撒きおよび怪文書の配布は厳禁」など、具体的な禁止行為を明記した立て看板やプレートで警告表示をします。

(Amazon.comサイト「ブランド: DGDHDG」より)
なお、前者のような汎用的な警告表示はAmazonなどでも簡単に入手が可能ですが、後者のような個別具体的な行為を禁じる警告表示は、ネット上でなかなか見付かりません。そのため、自社で掲示物を作ることがありますが、そういった場合、印刷物をそのまま貼っただけではいかにも安っぽく、他のお客様に悪印象です。ラミネート加工をしたり、安価なもので良いので額装したりすることをお勧めします。
外部の専門家との連携体制(弁護士、医師、専門のコンサルタントなど)
今まさに嫌がらせを受けていたり、既に発生している経済的損失を回復させたい時には、警察と並行して弁護士にも相談をしましょう。他所でも書きましたが、警察は被害状況等に応じて捜査や逮捕をしてくれるかもしれませんが、既に発生している被害の回復まで対応してくれる訳では無いため(取り調べ中、犯人に被害回復を求めることはありますが)、損害賠償請求を希望の場合は弁護士との連携が欠かせません。
なお当社では、有事の際の対応は避けられませんが、何よりも重要なこと未然防止であると考えています。嫌がらせの伴うカスハラが起きた場合、警察や弁護士にお金と時間を使って何とか解決しても、根本原因の除去や再発防止策が講じられていなければ(同じ弱点を抱えたままでは)、最悪の場合、今後も同じような嫌がらせが起き続けてしまいかねません。そのため、嫌がらせの伴うカスハラをしっかり振り返り・分析し、対策などをガイドライン、マニュアル、研修などに反映させていくことが極めて重要です。
もし、上記の様な再発防止策の構築を自社内で対応できない場合は、外部の専門家と積極的に連携することを強くお勧めします。自走できるようになるまでは専門家のノウハウを活用する方が、結局、費用的にも時間的にも品質的にも満足できる可能性が高いです。
まとめ|「たかが紙切れ」と軽視せず、組織的対応で終結させる
ビラや怪文書が、一見平静で危険を感じないような内容だったとしても、「たかが紙切れ」などと軽視することは絶対に厳禁です。問題は内容ではなく、そういった文書を不特定多数に配ったり、敷地内に侵入したり、といった行動をしていることです。既にそういった行動に出ているということは、もしもその行動で相手の気が晴れなければ、さらにエスカレートした行動に出る可能性があり、暴力や怪我に発展する可能性もあります。そのため、嫌がらせ行為を察知したなら、個人任せにせず組織的に対応して行くことが極めて重要です。
本コラムで紹介した内容について、無料相談をご希望の場合は、下記からお気軽にご連絡ください。