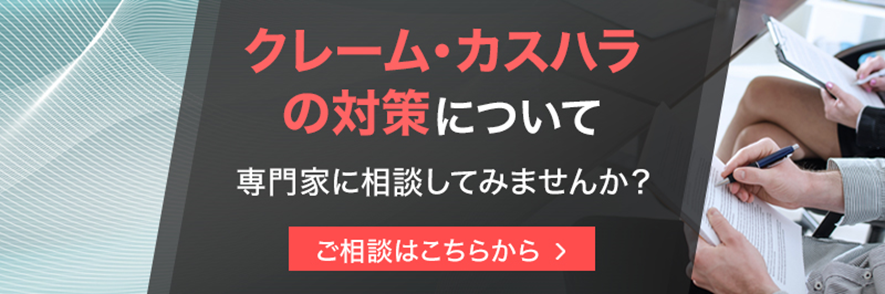なぜ今、サービス業のカスハラ対策が必要か? 事例に学ぶ5つの対策

令和7年4月に東京都でカスハラ防止条例が施行され、同年6月には企業にカスハラ対策を義務付ける改正労働施策総合推進法が成立しました。この法律は、企業の事業主に対して、従業員がカスハラにより就業環境を害されないよう、必要な措置を講じることを義務付けるものであり、早ければ2026年中に施行されます。
東京都では企業向けに奨励金(カスタマーハラスメント防止対策推進事業)の募集を始め、当社のある埼玉でも、2026年7月現在、県議会において、県独自の条例案が検討されています。
一方、「カスハラには毅然と対応する」と言っても、明確なルールが無ければ適切な対応はできず、正当なクレームまで排除し、CSの低下になりかねません。企業にとって、給与の減資となる売上を与えてくれる唯一つの存在は顧客なので、その顧客とのいたずらな対立は避けるべきです。
中でも特にサービス業(※)は、顧客至上主義の文化が色濃く残っているうえ、以下のように、ハードクレームやカスハラが起きやすい特徴を持っています。
| ●物へのクレームが提供元企業に向かいやすいのに対し、サービスへのクレームは提供者である従業員個人に向かう。 ●意思決定が感覚的で、個人の好き嫌いが(場合によっては機嫌の良し悪しが)評価に直結する ●サービスの提供者と顧客が直接接しながら提供するため、提供元と直接的な接点が多い ●人がサービスを提供するため、品質のバラツキが多い ●事業者や従業員に実践的なノウハウが少ないため、火が小さいうちに消火できないことが多い |
そこで本コラムでは、主にサービス業向けに、カスハラの特徴と対策について解説します。
(※)理容や美容、ホテルや旅館、タクシー、配送、塾、コンサルティングなど、主に人が直接提供するサービスを指しています。ただし、飲食業や小売業、通販のカスタマーサポートなど、物の提供が伴う場合でも、その中の顧客対応部分はサービス業に該当する場合があります。
なぜ今、サービス業のカスハラ対策が必要か? 事例に学ぶ5つの対策
カスハラとは?(カスタマーハラスメントとは)
カスハラとは、「カスタマーハラスメント」の略であり、一般的には、暴行や土下座要求の伴う激しいクレームを指して呼びます。しかし、ハードクレームとカスハラは、実は同じものではありません。
カスハラの定義(『厚生労働省カスタマーハラスメント対策マニュアル』より)
厚生労働省が公開している『カスタマーハラスメント対策企業マニュアル』では、以下の様に定義しています。
| 企業や業界により、顧客等への対応方法・基準が異なることが想定されるため、カスタマーハラスメントを明確に定義することはできませんが、企業へのヒアリング調査等の結果、企業の現場においては以下のようなものがカスタマーハラスメントであると考えられています。 顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの。 |
程度の問題はありますが、お客様から強く指摘をされたからと言って、そのクレームの直ちにカスハラに該当する訳ではありません。しかし、サービスの改善や権利の実現を求める正当なクレームがある一方、そうでは無い悪質なカスハラは、業績の低下や従業員の離反など企業に深刻な悪影響を与えます。
サービス業におけるカスハラの具体例
当社が聴いた中には、以下のような例がありました。
- 「おい!」「呼ばれたら大きな声で返事をしろ」「早くこっちに来い!」など、命令口調で対応された。
- 「デブ」「ババア」「ハゲオヤジ」など、こちらのミスと無関係な容姿の侮辱をされた。
- 1時間近くにわたり、大声で「馬鹿野郎!」などと怒鳴られ続けた。
- (男性の従業員に対し)頭の上に手を置いたり、額をつけながら凄んだり、喧嘩腰で挑発された。
- (女性の従業員に対し)肩を触られたり、「責任をもって対応してもらいたいから」と言ってしつこく電話番号を訊かれたりした。セクハラだと思ったが、お客様からのクレームだったので言い返せなかった。
- 煙草の煙を吹きかけられた。
- ビールの空き缶を食べかけのラーメンに突っ込んで返された。味が気に入らなかったら率直に言ってくれるならまだしも、それは無いだろうと思った。
- 店の備品を目の前で床に捨てられた。注意したら「片付けんのがテメェーの仕事だろ」と言われた。
- コールセンターで、聞こえなかったので聞き返したら「耳糞溜まってるのかカス!」と怒鳴られた。
上記の中には、オーダーの通し忘れなど、お店の側でお怒りの原因を作ってしまっていた例もありましたが、だからと言って、人格否定をして良い訳がありません。また、これらはいずれも対面接客の中で行われたため、従業員は衆目の眼前でお客様から痛烈に面罵されることになり、従業員にとって強烈なストレスだったことは誰の目にも明らかでした。実際、その後退職してしまった方も何人かいました。
このように対面接客側サービス業におけるカスハラは、従業員にとっても心身に甚大な被害をもたらします。
サービス業におけるカスハラの見極めの難しさと、見極めるポイント
厚生労働省の『カスタマーハラスメント対策企業マニュアル』では、カスハラの判断のポイントとして、以下の2点に対する具体例を挙げています。
- 顧客等の要求の内容が妥当性を欠く場合
- 要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当な言動
しかし、サービス業の場合は、提供する側もされる側も人的な接触を介しているため、カスハラと感じるか否かも人により大きく変わります。例えば飲食店で飲み物を落としてしまった時、睨まれたり舌打ちされたりするだけで怖いと思う人もいれば、怒鳴られても物怖じしない人もいます。そのため、お客様の態度が「内容が妥当性を欠く」に該当するか否かを、その場その場で適切に判断することは簡単ではありません。
そこで当社では、サービスの提供プロセスを分解し、例えば、「配膳中にトラブルが起きるとしたら●●のようなケース」「会計中にクレームになるとしたら▲▲のようなケース」などと具体化し、関係者に共有しておくことをお勧めしています。カスハラと思われる状況は、発生してしまうと極めて強いプレッシャーに晒されます。そのため、予め顧客との接点からリスクを洗い出し、上記のような具体例にしたうえで、それに当てはまるか否かの判断基準を明確化しておくことが有効です。
【参考記事】
【カスハラとは?】事例に基づいた具体的な基準と、対応のポイントを解説
法的な観点と企業の対応責任
前段で述べた通り、カスハラはクレームの延長ではなく、セクハラやパワハラと同じハラスメントの一種です。
そのため企業は、自らもカスハラの被害者というだけでなく、従業員をカスハラ被害から守るため主体的・積極的な対策を講じることが求められます。
具体的には、従業員に対する安全配慮義務(労働契約法 第5条・労働者の安全への配慮)や各自治体におけるカスハラ対策条例への対応義務が課されることになります。
サービス業の特徴を理解する
他所でも何度か伝えて来ましたが、当社は、カスハラを減らすための最良の方法は未然防止であると考えています。ですから、カスハラへの具体的な対策を検討する前に、まず、サービス業の特徴をもう少し掘り下げて理解することが重要です。そうすることにより、サービス業ではどのような場面でハードクレーム/カスハラが起こりやすいかを踏まえ、どのような対応が有効なのかを、柔軟に検討することが可能です。
無形性(サービスには形が無いため、目で見たり手で触ったりができない)
温泉旅館における温泉の質、ラーメン屋におけるスープの味などの他、当社のようなコンサルタントにとってのサービス内容も、事前に目で見たり手で触ったりすることで品質を確認することができません。そのため、「話が違った!」「イメージと違った!」といったクレーム/カスハラの原因になりやすいです。
対策としては、温泉の効能やスープのこだわりなどを掲示し、品質を具体的に伝えたり、湯舟や器を高級感のあるものにしたりするなど体感品質を高めることで、品質に起因するクレーム/カスハラを抑制することが考えられます。
当社でも、具体的な支援内容を料金表として予め公開し、ご希望者にはサンプル動画を共有するなどして、品質の有形化を進めております。
品質の変動性(誰が提供するか、いつ提供するか、などにより品質が変る)
典型的には、美容、利用、サロンなどのビューティービジネスが挙げられますが、当社の様なコンサルタントも該当します。品質の均一性が保ち難いため、「この前と違う!」といったクレーム/カスハラの原因となりやすいです。また、実際の品質は同じであっても、サービスを受ける側のコンディションによって評価が分かれやすいことにも留意が必要です。
対策としては、事前ヒアリングの徹底、提供プロセスの標準化、ゴールのすり合わせ、マニュアル化や研修・トレーニングなどが有効です。当社でも、サービスの提供プロセスを標準化し、ご契約前に予めお示しすることで、一定の品質水準を保てるように工夫しています。
サービスの消滅性(人が直接提供するため、在庫を保有できない)
サービスを提供する側とされる側が必ずその場にいなければならず、生産と消費が同時に行われるため、貯蔵ができません。そのため、急な需要の変動への対応が難しく、在庫切れや「待たされた!」といったクレーム/カスハラの原因になりやすいです。典型的には、ビューティービジネス、コンサルタント、スクールビジネスなどが挙げられますが、飲食店や物の販売であっても、従業員による人的販売の場合には接客部分が該当します。
対策としては、大きく「需要管理」と「供給管理」に別けられます。
需要管理の例
- 時間帯割引、曜日割引、季節料金などを導入し、需要のピークを非ピークに移動させる。
- 特別なイベントや優待サービスなどで、非ピークの需要を活性化する。
- 予約システムの導入や「現在の空席状況」の公開をすることで、非ピーク時の需要を埋め、需要を平準化する。
供給管理の例
- オーダーや会計などのセルフサービスを導入することで、サービスの供給能力を高める。
- パートタイムの従業員を活用することで、ピーク時の供給能力を高める。
- テキスト化や動画化により、貯蔵ができ、かつ同時に複数の相手にサービスを提供できる仕組みを作る。
カスハラを放置するリスク、企業への悪影響
カスハラを放置することは、企業業績に大きな悪影響を及ぼすリスクがあります。特に、従業員を守るために適切な配慮をしなければ、安全配慮義務違反としてペナルティを受ける可能性さえあります。
サービス業は、製造業とは異なり、「ここのスペックを●%向上させればクレーム/カスハラが▲%減少する」といった数値の管理が難しく、クレーム/カスハラを減らすためにはサービスの提供プロセス全体を見直す必要があるといった特徴があります。
当社は、多くのサービス業の支援を通じ、クレーム/カスハラの削減から個客満足度の向上までワンストップでの支援が可能です。組織的な対策について専門家への相談を希望の方は、下記からお気軽にご相談ください。
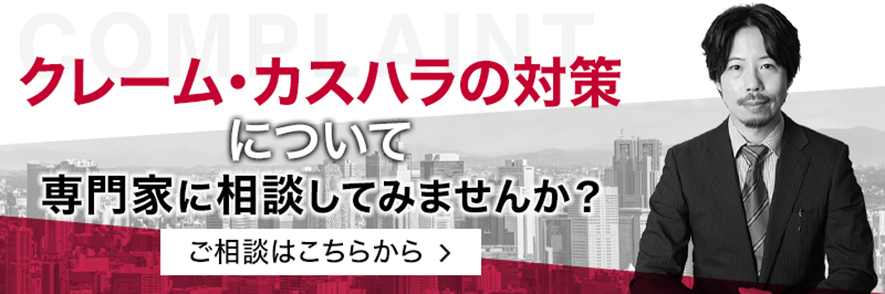
【業種別】サービス業におけるカスハラの具体的な事例
ここからは、対人接客の伴うサービス業における、カスハラの具体的な事例を確認して行きます。
小売業、販売業、飲食業など、対面型接客業におけるカスハラ事例
飲食店.comが行ったアンケートによると、カスハラ被害のトップ5は以下のようなものでした。
- 必要以上に説教をされた(56.4%)
- 備品を持ち帰られた(31.2%)
- 長時間、居座られ続けた(30.9%)
- 料理を作り直しさせられた(19.4%)
- 故意にドタキャンをされた(19.1%)
また、上記の他にも、大声での暴言、口コミサイトやSNSなどでの誹謗中傷、従業員の顔写真を無断でSNSに投稿するなど、多岐にわたります。これらはいずれも、そのお店に対する満足度の低下や(横でカスハラをされると、いわゆる「飯が不味く」なってしまう)、運用コストの上昇(備品の持ち帰りや料理の作り直し)など、企業にとって深刻な影響を与えます。当然、従業員の心身の疲弊も深刻です。
【参考記事】
ハードクレーム・カスハラ対応 | 飲食店など対面接客で「態度が悪い」と言われたら
宿泊業・観光業での事例
宿泊や観光などの業種では、以下のようなクレーム/カスハラを聞きます。
- 内容への不満(予約が取れてない、申し込んだプランと違う、間取りの説明が無かった)
- 設備への不満(エアコンが弱い、シャワーが冷たい、Wi-Fiが切れる)
- 過剰サービスの要求(数時間毎の清掃、緊急性の低いことに対する早朝や深夜の対応)
- スタッフへの不満(態度が悪い、説明が分かりにくい、依頼通りにやってくれなかった)
宿泊や観光などの業種が、飲食店や販売業など他のサービス業に比べ大きく違う点としては、基本的に装置産業であることが挙げられます。
ホテルや温泉旅館などの利用客は、もちろん、料理や接客なども楽しみにしていますが、その宿泊施設を利用することが第一の目的です。従って、ホテルや温泉旅館などの従業員は、サービスや接客に対してだけでなく、施設や設備に対するクレーム/カスハラを受ける可能性があることに留意が必要です。
美容・理容・サロンなどビューティー業界での事例
美容・理容・サロンなどのビューティー業界では、以下のようなクレーム/カスハラを聞きます。
- 問題無いサービスに対して、無償でのやり直し要求(イメージと違う、自分でセットできない)
- サービスに関係無い物の要求(試供品、限定ノベルティ、スタッフの私物など)
- ネットやSNSへの晒し、口コミでの理不尽な低評価(個人名を挙げて事実と異なる非難をするなど)
美容・理容・サロンなどのビューティー業界は、「イメージを売る仕事」である点が、小売りや販売などの「物を売る仕事」やホテルや旅館など「体験を売る仕事」と大きく異なる点です。
イメージは顧客の心の中に形成されるものなので、企業側が完全にコントロールすることはできません。そのため、期待が大きければ大きいほど、クレーム/カスハラになるリスクも高まります。また、サービスは必ず、従業員と顧客との直接的なコミュニケーションと共に発生するため、相性にも影響を受けやすい点にも、留意が必要です。
【参考記事】
【カスハラ対策】「ネットに晒す」「SNSで晒す」から従業員を守るためには!
カスハラから従業員を守るために組織ができる5つの対策
他所でも伝えて来ましたが、クレーム/カスハラは、起きてからでは適切に対応することは困難です。そのため当社では、以下の様に予め組織的な対策を講じることをお勧めしています。
専門家への相談
クレームやカスハラへの対策において、最も悪い対応は丸投げですが、次に悪い対応は丸抱えです。
対人接客の伴うサービス業におけるクレーム/カスハラへの対策には、前述の通り独自のポイントがあるので、自社に対策のノウハウが無い場合は、専門家に相談しながら対策を構築するのが近道です。
ガイドラインの作成
カスハラへの対策は、その場その場で対応しているだけだとモグラ叩きになってしまい、せっかく苦労して対応しても何を達成したか分からないということになりかねません。そこで、組織全体として目指す顧客対応やカスハラへの対応方針、そのための組織としての支援などを、ガイドラインとして明確化します。
また、その中でも顧客向けに重要なポイントは、ポスターにして掲示することが有効です。
【参考記事】
カスハラ対策ガイドライン(基本方針)作成の5ステップを具体的に解説
対策のマニュアル化
業種、業態、客層など様々な要素によって、クレームやカスハラの傾向も大きく異なります。そのため、予め自社のビジネスモデルやカスタマージャーニーマップのリスクを確認し、具体的な対策を講じ、それをマニュアル化することで従業員に共有します。
マニュアルと言うと、いわゆる作業手順書のようなものをイメージする方が多いようですが、それだけに限りません。トークスクリプトや業務フロー図なども重要なマニュアルです。自社のビジネスモデルやカスハラ対策に合ったマニュアルは何かを考え、柔軟に作成して行きましょう。
【参考記事】
使えるクレーム・カスハラ対策マニュアルの作成 | 3ステップで解説
従業員への研修・トレーニング
マニュアルを作成しても、トラブルが生じてから初めて参照するのでは効果薄です。例えば、宿泊業における改正旅館業法に基づいた宿泊拒否や、暴行を回避しながらの警察への通報などは、理屈だけでなく具体的な判断基準や対応手順を組織全体で共有できなければ、咄嗟の対応は困難です。可能な限り事前に、理論的な研修に加えて、モニタリングやロープレなどアクションの伴うトレーニングを実施しましょう。
ポイントは、できるだけ短い単位に小分けして研修・トレーニングを作成することです。1研修あたり1時間以上も要するとなると、現場から人を抜けず、研修を実施すること自体が困難です。しかし、5分10分でスクリプトを読み合わせる程度であれば、朝礼中に実施することも可能です。
また、研修やトレーニングが困難な場合は、朝夕礼や閑散機などで見れるような短めの動画マニュアルを作ることで、仮想的なトレーニングとすることも有効です。
【参考記事】
マニュアルだけじゃない!クレーム・カスハラ研修を成功させる5ステップ
相談体制の整備
どれほどマニュアル化やトレーニングを実施しても、相手があることなので、上手くクローズできない場合もあります。そのような場合、上司にエスカレーションするように勧める対策本などを目にすることがありますが、上司も人間であり、特別なトレーニングを積んでいない限り、適切にクローズできるとは限りません
そこで、例えば法的な判断やより踏み込んだ対応方針のアドバイスなど、現場での判断が困難な内容を適宜エスカレーションできるように、相談先を確保しておくことは極めて重要です。 また、相談先は必ずしも業務的な内容だけでなく、悪質なクレームやカスハラへの対応によるストレスなどで心身に不調を生じている場合など、メンタルヘルスケアのための相談窓口も必用です。
【参考記事】
カスハラが発生したら? | 退職を防ぐ、組織的対策の6つのポイント
まとめ:カスハラ対応は、顧客満足度との両立が重要
対人接客の伴うサービス業では、カスハラ対策と言うと、「毅然と対応する」といった言葉に代表されるように、顧客満足の考え方と対立すると誤解されがちです。しかし、本コラムで説明して来た通り、サービス業の特徴を正しく理解し、その特長に応じた予防策や対策を講じることで、顧客満足度の向上とカスハラへの対策は両立可能です。
一方、そういった両立を目指さなければ、企業に売上を与えてくれる唯一つの存在である顧客を敵視した対策を講じることになり、カスハラは少なくなっても、中長期的には、それ以外の大多数の顧客満足度を低下させてしまう可能性もあります。そのため、自社のビジネスモデルやサービスの提供プロセスを客観的に見渡し、自社の特性に応じた対策を講じ、従業員に研修して行くことが、サービス業では極めて重要です。
本コラムで解説した内容について、専門家のアドバイスを受けてみたい方は、下記からお気軽にご連絡下さい。