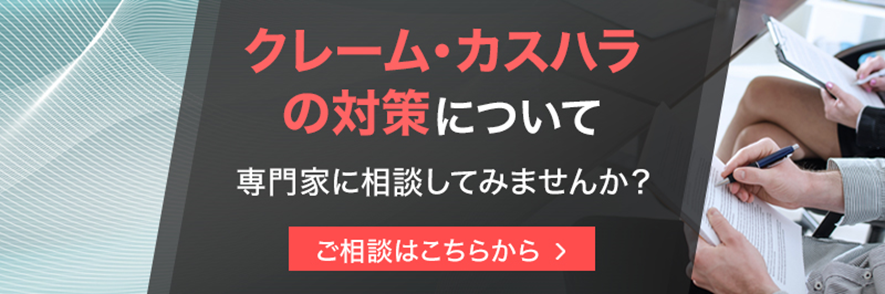【カスハラ対策】令和8年施行予定|労働施策総合推進法改正への対応

令和7年の通常国会では、カスタマーハラスメント(以下「カスハラ」)への対策の義務化を含む『労働施策総合推進法』の改正が行われました。
実は、令和7年の通常国会では、他にも他の労働関係法がいくつか改正されています。しかし、労働施策総合推進法の改正については、注目度が高いうえ、従来のハラスメント対策とは異なる対応を求められ、企業独自の対策だけでは遺漏が生じる可能性があるため、本コラムで詳しく解説いたします。
なおこの法律は、令和7年6月4日に改正法が成立・公布され、公布から1年6ヶ月以内(早ければ令和8年10月)に施行される予定です。そのため、これから決まる部分も多いと思われ、現時点では具体的な対策が難しいのも事実です。しかし、そうであっても、現時点の情報を整理し組織の方向性を予め確認しておき、できる対策は初めておくことは、対策の実行力を高めるのに有効なので、参考にしていただければ幸いです。
※本コラムはカスハラ対策のコンサルタントとしての見解であり、具体的な法解釈は、監督省庁に確認するなどしてください。
【カスハラ対策】令和8年施行予定|労働施策総合推進法改正への対応
改正労働施策総合推進法における事業者の義務の明確化
まず、カスハラの定義を確認します。
改正労働施策総合推進法では第三十三条においてカスハラを「事業主は、職場において行われる顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者(次条第五項において「顧客等」という。)の言動であって、その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたもの(以下この項及び次条第一項において「顧客等言動」という。)により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、労働者の就業環境を害する当該顧客等言動への対応の実効性を確保するために必要なその抑止のための措置その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。」と規定しています。
少し長いので、法改正と併せて交付されたリーフレットでカスハラの定義を確認すると、以下の3つの要素をすべて満たすものとなっています。
| ・顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者(以下「顧客等」)が行う ・社会通念上許容される範囲を超えた言動により ・労働者の就業環境を害すること |
上記3点の具体的な内容は、今後、施行時期までに定められる予定です。しかし、現時点でも過去の労働政策審議会の報告においては、以下の様に考え方が示されており、基本的な考え方は踏襲すると思われます。
| 「顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者(以下「顧客等」)が行う」とは |
|---|
| ・「顧客」には、今現在利用中の顧客と、今後利用する可能性のある潜在的な顧客の、両方を含む。 ・「施設利用者」とは、施設を利用する者をいう。施設の具体例としては、駅、空港、病院、学校、福祉施設、公共施設などが挙げられる。 ・「当該事業主の行う事業に関係を有する者」とは、例示している者に限らず、様々な者が行為者として想定されることを意図する。法令上の利害関係者だけでなく、施設の近隣住民など、事実上の利害関係者も含む。 |
| 「社会通念上許容される範囲を超えた言動により」とは |
|---|
| ・権利の濫用や逸脱にあたるようなもの。社会通念に照らし、当該顧客等の言動内容が相当性を欠くもの。手段・態様が相当ではないもの。 ・「社会通念上相当な範囲を超えた言動」の判断は、「言動の内容」と「手段・態様」に着目し、総合的に判断するのが適当。また、上記のうち一方のみでも社会積年上相当な範囲を超える場合もありえる。 ・事業者または労働者の側の不適切な対応が端緒となっている場合もあることに留意する必要がある。 |
| 「労働者の就業環境を害すること」とは |
|---|
| ・労働者が身体的または精神的に苦痛を受け、就業環境が不快なものになったために能力の発揮に重大な悪影響が生じているなどの、その労働者が就業するうえで看過できない支障が生じていること。 ・「平均的な労働者の感じ方」とは、「同様の状況で当該言動を受けた場合、社会一般の労働者であれば、就業するうえで看過できないていどの支障が生じると感じるような言動であること。 ・言動の頻度や継続性は考慮要素となるが、身体的または精神的な苦痛の程度が強い場合には、1回でも就業環境を害する場合があり得ること。 |
なお、東京都など一部の自治体では先行して独自に条例が制定済の場合もあります。これらは、大筋では改正労働施策総合推進法と同じカスハラ対策であっても、地域性や検討経緯によっては規程が異なる場合があるため、自社の対策を検討する際には、必ず、事業所所在地の条令やその検討経緯などを確認することをお勧めします。
事業主の義務
過去の厚生労働省の『職場のハラスメントに関する実態調査』によれば、セクハラ、パワハラに続いて労働者からの相談件数が多いのがカスハラでした。そのため、今回の改正ではこのカスハラに対して、事業主に雇用管理上の措置が義務として科されることが規程されました。
事業主が講ずべき雇用管理上の措置
改正労働施策総合推進法の三十三条では、事業主に対して以下の通り雇用管理上の措置を求めている他、同条の2項では、カスハラ被害等の相談または事業主による相談対応への協力したことに対する、不利益取扱いの禁止規定が定められています。
| ・当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 ・労働者の就業環境を害する当該顧客等言動への対応の実効性を確保するために必要なその抑止のための措置 ・その他の雇用管理上必要な措置 |
また、三十四条では、事業主の責務として、労働者のカスハラに対する理解や関心を深めるために研修等の実施や、国の実施する措置への協力義務を定めている点も重要なポイントです。
事業主の責務は、従来から安全配慮義務として認識されており、実際、厚生労働省のカスタマーハラスメント対策企業マニュアルでも判例などが紹介されていました。しかし、安全配慮義務は責任範囲が広範である一方、カスハラに対する個別具体的な対策の要求がありませんでした。
それに対し、今回の労働施策総合推進法の改正では、カスハラに対して事業主が講ずべき雇用管理上の措置が具体的に定められ、「やらなければいけないこと」が明確化された点が大きな特徴です。
他の事業主から協力を求められた場合の対応
今回の法改正では、他の事業主から雇用管理上の措置に関し必要な協力を求められた場合には、それに応じるように努めなければならないことが規程されました。
上記は努力義務ですが、それに加えて、今後作成が予定されている指針においては、他の事業主から協力を求められたことを理由に不利益取扱いを行うことが望ましくないことや、事実確認の結果として、協力を求められた側の事業主の労働者が実際にカスハラ行為をおこなっていた場合には、就業規則などに基づいて適切な措置を講じることが望ましい旨が記載される予定です。
法改正は決まりましたが、施行は令和8年中と想定され、まだ十分に時間があるので慌てて対応する必要はありません。一方、今回の法改正の最大のポイントは、カスハラをする顧客への規制ではなく、事業主の義務が明確化されたことであり、施行日以降は全ての企業組織が義務の対象になることには注意が必要です。
当社では、まだ十分に時間があるからこそ、カスハラに限定した対策ではなく、自社の顧客対応全体に対する在るべき姿をしっかり検討する機会にすることをお勧めしています。
上記について、専門家へのご相談をご希望の場合は、お気軽にご連絡ください。
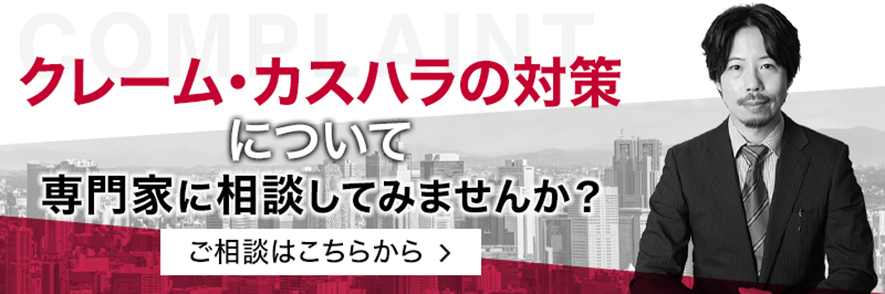
他のハラスメント対策とカスハラ対策との違い
ここからは、法改正を見据えた組織の実務について検討して行きます。そのため、前提として、労働施策総合推進法の改正において企業に義務化されたカスハラ対策は、セクハラ、パワハラ、マタハラなど従来のハラスメント対策とは構造的に違っていることを理解しておくことが重要です。
具体的には、以下の通りです。
| セクハラ、パワハラ、マタハラなど従来のハラスメント対策 |
|---|
| 従来のハラスメントは基本的には会社内部で行われる行為であり、被害者も加害者も自社の従業員であることが大半です。そのため、以下の特徴が挙げられます。 ・加害者になる可能性のある者に対し、会社が講じる措置についても浸透しやすい ・自社の従業員がハラスメントの加害者になることを想定して教育、注意喚起、懲戒規程の定めなどを予め講じることができる ・被害の把握についても、全く突発的ということは少なく、必要なら綿密な事実確認などの調査も可能 |
| カスハラへの対策 |
|---|
| カスハラは、被害者は自社の従業員ですが、加害者は顧客などの外部の存在です。そのため、会社内の従業員に比べて予防面ではできることに限りがあります。 ・加害者になる可能性のある者に対し、周知や注意喚起には限界がある ・社内の従業員のように綿密な教育を社外の顧客に対しても実施することは困難であり、対処療法を避けられない ・どんなに綿密に対策していたとしても、突発的に理不尽なカスハラを受ける可能性は残ってしまう |
今回の法改正と合わせて公開された関係通知及びリーフレットにも、以下の内容が記載されています。
| ・事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発 ・相談体制の整備・周知 ・発生後の迅速かつ適切な対応・抑止のための措置 |
上記で説明した通りカスハラは、自社の従業員が実際にカスハラ被害を受けた場合には、他のハラスメント対策と異なり社外に対する対応が前提となります。
そのため、他のハラスメント対策と措置の名称等は類似していたとしても、その内容は、実際のカスハラを想定して、それに対してどう対応し、どう判断し、どうクロージングするのかといったことを、予め具体的に検討した内容である必要があります。
その他の対策の具体例
カスハラ対策としては一般的に、ガイドライン(基本方針)作成、判断基準の明確化、対策マニュアルの作成、研修・トレーニングの実施、相談体制の構築が有効とされています。
それぞれ、以下のリンク先で詳述しておりますので、参照いただければ幸いです。
ガイドライン(基本方針)の作成
カスハラ対策ガイドライン(基本方針)作成の5ステップを具体的に解説
判断基準の明確化
【カスハラとは?】事例に基づいた具体的な基準と、対応のポイントを解説
対策マニュアルの作成
使えるクレーム・カスハラ対策マニュアルの作成 | 3ステップで解説
研修・トレーニングの実施
マニュアルだけじゃない!クレーム・カスハラ研修を成功させる5ステップ
相談体制の構築
カスハラが発生したら? | 退職を防ぐ、相談体制作りの6つのポイント
就業規則におけるカスハラ対策規程の整備
上記のような対策だけでなく、雇用管理上の措置において非常に重要な要素として、就業規則における対策規程の整備が挙げられます。就業規則には通常、自社の従業員によるハラスメントの禁止、会社による不利益取扱いの禁止、などを定める役割があります。そのため、カスハラに対して会社がどのような雇用管理上の措置を行うとしても、規程の作成は不可欠です。
他のハラスメントの規定では基本的に、被害者・加害者ともに自社従業員であることを前提として、「従業員は●●ハラスメントをしてはならない」などと強調されていることが多いです。しかし、前述の通りカスハラの加害者は、取引先の従業員の場合もありますが、B to Cのビジネスでは社外の顧客であることが多いです。また、今回の労働施策総合推進法の改正ではB to Bのカスハラも想定されており、この場合には加害者は自社の従業員になりますが、被害者が社外の取引先などということになります。そのため、以下のようなポイントを盛り込んでおくことを検討しましょう。
| カスハラを防止するための規定 |
|---|
| ・自社の従業員に対し、カスハラとして禁止する行為の規定 ・自社の従業員がカスハラ被害を受けた場合の禁止行為の規定 ・自社の従業員がカスハラ被害を受けた場合の推奨行為の規定 |
また、もう一つ重要なポイントとして、現時点では努力義務や協力義務とされている以下のような事項について、懲戒対象の処分とすると定めるなどの対応により実効性を高めることも有効です。特に、以下のような事項に対してはぜひ検討したいところです。
| 努力義務や効力義務の実効性を高めるための規定 |
|---|
| ・従業員に対し、他の事業主から雇用管理上の措置に関し必要な協力を求められた場合に応じること ・主幹部署に対し、労働者のカスハラに対する理解や関心を深めるために研修等を実施すること ・主幹部署に対し、国の実施する措置に協力すること |
最後に|法改正への対応はカスハラ対策ではなく顧客満足向上の機会
『労働施策総合推進法』の改正においてカスハラが盛り込まれたことは、従業員が安心・安全に働くためには、極めて大きな出来事です。
一方、これまで見て来た通り、この法改正により様々な義務が課されるのは、基本的には事業主です。令和8年12月までに施行された後は、全ての組織がこれらの義務に対応していくことが求められます。もし対応しなければ、不幸にしてカスハラが発生した時、事業主はその責任を厳しく追及される可能性もあることには注意が必要です。
しかし、見方を変えれば、今回の法改正は自社の顧客対応を根底から再検討し、安心・安全に働ける環境を提供することで従業員満足度を高め、顧客満足度を高める仕組みを作るための絶好の機会です。そのような取り組みができる企業と、受動的にカスハラ対策だけを行う企業では、その将来に大きな差異が生じることになるはずです。
法改正への対応や、自社の顧客対応について、専門家に相談をご希望の方は、下記からお気軽にご連絡いただければ幸いです。