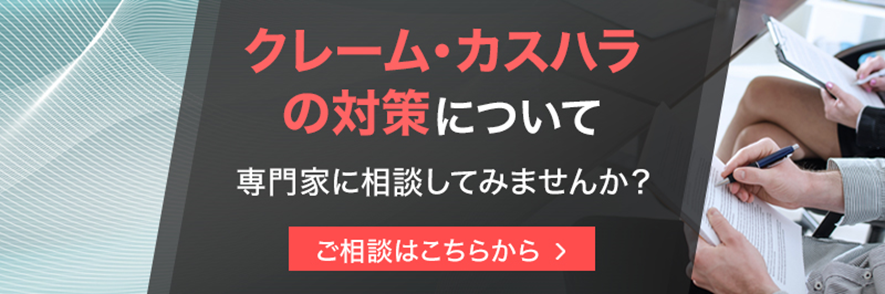ビジネスネームで従業員をカスハラから守る|導入の7ステップを具体的に解説

最近、名札への本名を非開示にした企業のニュースを目にするようになりました。実際、近所のコンビニや居酒屋などでも、「K・H」とイニシャルだけだったり、「店員」としか表示されていなかったり、といった名札を目にすることは珍しくなくなっています。行政でも、2025年には大阪府寝屋川市が、カスタマーハラスメント(以下「カスハラ」)対策と職員のプライバシー保護を目的として、希望者へのビジネスネーム使用を認めたことが報道されました。
従来からカスハラは、宿泊業、飲食業、小売業、医療や福祉、市役所などの行政窓口といった接客を伴うサービス業においては、従業員が暴言や暴力、不当な要求に加えて、無断撮影やインターネット上への動画流出などの深刻なカスハラ被害に遭う例がありました。そういったカスハラへの対策として、上記のようないわゆるビジネスネームは、従業員の安心と安全を確保し、心理的な負担を軽減するための有効な方法です。
そこで本コラムでは、ビジネスネーム導入について、具体的に解説します。
ビジネスネームで従業員をカスハラから守る|導入の7ステップを具体的に解説
ビジネスネームの導入目的とその効果
ビジネスネームを導入する主な目的は、以下の3点です。
従業員のカスハラ被害の防止
相対による顧客対応の場で本名を掲示することは、場合によっては大きなリスクを伴います。例えば、店頭での対応をきっかけに、インターネットの評価サイトやSNSなどで本名や顔が分かるように動画などを公開されたりする例の他、本名から自宅が突き止められてストーカー被害に遭う可能性もあります。
ビジネスネームを導入することは、上記のようなカスハラ被害を防止し、従業員が安心して業務に集中できる環境作りに有効です。
従業員の心理的安全性の確保
ビジネスネームを導入しても、カスハラを完全に予防することはできません。しかし、それでも本名を知られなければ、インターネット上に本名を書きこまれたり、自宅や交友関係を調べられたり、といった追加的な被害はある程度防ぐことができます。
もちろん、それで十分と言うことはありませんが、少なくても、プライバシーに関わる情報が外部に晒されていないことは、従業員の心理的安全性の確保に寄与します。
従業員に配慮した多様な働き方への対応
例えば、結婚や離婚など婚姻関係の変更後も旧姓を使い続けたい従業員や、性自認に配慮した名前の使用を希望する従業員に対しても、ビジネスネームの導入は、他の従業員との公平性を保ちながら配慮することができます。
上記のように、合理的な範囲で企業が多様性を尊重し、柔軟な働き方に配慮した働き方を支援することは、従業員からのエンゲージメントや企業に対する社会的評価の向上にも貢献します。
ビジネスネーム導入の7ステップ
ビジネスネームをスムーズに導入するためには、以下のようなステップに沿って準備をするのが有効です。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| 1 | 導入目的を明確にする。 まず、導入の目的を整理し文書化します。この時、「従業員のカスハラ被害の防止」、「従業員の心理的安全性の確保」、「多様な働き方への配慮」といった目的を明示することで、運用に一貫性が生まれ、社内への理解も得やすくなります。 |
| 2 | ビジネスネームの使用範囲を決定する。 対面接客、メール署名、オンライン会議の表示名、名刺など、具体的な使用範囲を決定する。 |
| 3 | 関連規程を整備する。 「ビジネスネーム使用規程」を作成し、必要な承認を得たうえで、社内への周知を実施します。 なお、カスハラ対策の規程を作成している場合は、先の中にビジネスネームの使用について追加しても良いです。 |
| 4 | 申請、承認、廃止などのワークフローを整備する。 ビジネスネームは、適切に管理できなければ、後述の通り会社としての責任範囲が不明となるなど不都合な場合もあります。そのため、使用を希望する従業員に対しては、理由を含めた申請の仕方、所属部門長による確認、管理部門による承認といったワークフローによる承認の流れを整備します。 |
| 5 | 管理台帳を作成する。 申請した従業員に対し、社員番号、本名、ビジネスネーム、申請理由、承認日、廃止日などを記録する台帳を作成します。これがなければ、最悪の場合、ビジネスネームと従業員との紐付けが分からなくなり、トラブルが起きたときの責任の所在が不明になります。そのため、関連規程内で管理台帳の取り扱いも定めた上、厳重なセキュリティのもとで管理をします。 |
| 6 | 社内への周知・説明を実施する。 目的、使用範囲、規程やワークフロー、FAQなどについて、従業員への周知・説明を実施します。 このとき、企業理念やミッション、経営戦略などを踏まえながら、「単に現場の責任を軽減させるためのものではなく、従業員が安心・安全に働ける環境を整備することにより、お客様により良いサービスを提供するための取組みである」など、経営者自身の言葉で目的をしっかり伝えることが重要です。 |
| 7 | 社外への共有を検討する。 地域性やビジネスモデルによっては、ビジネスネームを導入していることをお客様に分かってしまう場合があります。そのため、お客様が分かってしまった時に不要なトラブルを避けるために、WEBサイトや店内への告知の要否を検討します。 例えば、B to Bの場合やリピーターの多いB to Cの場合には、突然ビジネスネームを使い出すとお客様も混乱します。そのため、移行期間を設けながら、全体向けに「ビジネスネームを使用する理由」を公開するだけでなく、得意先には営業が個別説明をしたり、リピーターには専用の説明文を作成したり、といった対応を行います。 |
ビジネスネームは非常に便利で効果的ですが、適切なルールを制定し、従業員に目的を理解させながら導入しなければ、責任の所在が不明確になるため、従業員のサービスレベルの低下や企業としての改善機会の見落としの原因となる可能性もあります。
専門家に相談しながらの導入をご希望の場合、当社でも承っておりますので、お気軽に下記からご相談ください。
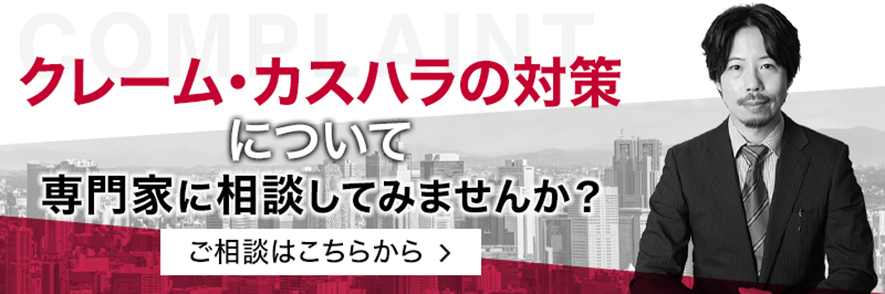
ビジネスネームの導入における5つの注意点
ビジネスネーム制度の導入は、多くのメリットがある一方、以下の5点を踏まえた制度設計をしなければかえってトラブルになる場合があることには、注意をする必要があります。
法令上、本名の使用が必須である場面を明確にする
雇用契約の締結、社会保険や税務関連の手続き、給与明細の発行などについては、本名での記載が必須です。そのため、ステップ2に沿って、ビジネスネームをどこまで使用できるかを確認し、関連各部署に共有しておかなければ、法令違反となる可能性があります。
責任の所在を明確にする
お客様とのやり取りでトラブルが起きたとき、対応した従業員が明確に特定できなければ、その後に必要な対応や再発防止策を講じることができないため、企業としてのリスクが大きく高まります。そのため、ビジネスネームを導入する場合でも、それが例えば「K・H」といったイニシャルや「レジ担当」などの表示だけだと、それが誰か一意に特定できなくなることには注意が必要です。
対策としては、「花村憲二郎」のような姓名で構成される重複の無いビジネスネームを作るほか、管理番号を併記しても良いでしょう。
個人情報保護に留意する
管理台帳では従業員の本名とビジネスネームが紐づいているため、万が一台帳の情報が漏洩すると、重大な事故・インシデントとなります。
ステップ3の規程整備では、「ビジネスネーム規程」を作成するだけでなく、情報セキュリティ管理規程などの関連規程にも反映させ、アクセス権の制御やアクセスログの保管など、情報セキュリティ対策を徹底します。
根本的にカスハラを無くす対策ではないことを理解する
ビジネスネームを導入しても、暴言や暴力そのものが無くなる訳ではないですし、こちらに一定の落ち度がある場合などは、「お前らが原因で迷惑してんのに、名前を教えねえってバカにしてんのか!?」などと更なるお怒りを誘発し、最悪の場合、カスハラになってしまう場合もあります。また、そうはならなくても、無断での録画や録音のインターネット上への流出自体は、ビジネスネームでは防げません。
ビジネスネームは飽くまでも、トラブルが起きた場合に本名の流出を防ぐ、対処療法的な者であることを予め理解し、従業員にも説明しておきましょう。
本名を知られてしまったときや、本名を訊かれたときの対応を決めておく
運用がこなれていない場合などでは、例えば従業員同士の会話をお客様に聞かれてしまったりなどで、本名を知られてしまう場合があります。また、酷いカスハラの場合には、ビジネスネームの導入を告知することで、お客様からストレートに「本名を教えろ!」と要求される場合もあります。
そういった場合に、本名を答えないとしても、代わりになんて答えるのか、具体的な対応を決めておく必要があります。
【参考記事】
【カスハラ対策】「ネットに晒す」「SNSで晒す」から従業員を守るためには!
なぜ今、サービス業のカスハラ対策が必要か? 事例に学ぶ5つの対策
脅迫、暴力などから従業員を守る!カスハラ対策で最も重要なポイント
市役所、自治体、公共機関|クレーム・カスハラ対策 カウンタートーク8選
カスハラ対応 | 飲食店など対面接客で「態度が悪い」と言われたら
「ビジネスネーム使用規程」の例
ビジネスネームの使用においては、前述のような注意点のほか、既存のお客様を混乱させないように配慮することも重要です。そこで、管理上極めて重要な「ビジネスネーム使用規程」について、盛り込む項目例を紹介します。
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 目的 | 「従業員のカスハラ被害の防止」、「従業員のプライバシー保護」、「多様な働き方への配慮」などと明確化します。 なお、目的を定めるときには、自社の経営理念やミッションだけでなく、カスハラ対策ガイドライン(または顧客対応ガイドライン)の内容と矛盾しない用に注意します。 |
| 定義 | 「ビジネスネーム」に対する会社の定義のほか、関連する重要な言葉の定義を定めます。 |
| 使用 範囲 | ビジネスネームの使用可能な範囲とともに、本名必須の手続きについて定めます。 |
| 申請、承認 | 申請方法や承認者を定めます。 |
| 禁止 事項 | 著名人やキャラクター名の使用、理由不明な申請、会社の品位や信用を損なうビジネスネーム、承認範囲外での使用など、禁止事項を定めます。 |
| 変更、廃止 | 変更や廃止を希望する場合の申請方法や承認者を定めます。 なお、安易な変更を防ぐため、回数制限も検討します。 |
| 管理 | 管理台帳の作成やその管理方法について定めます。 |
| 退職時の手続き | 従業員の退職後の取り扱いについて定めます。 なお、ビジネスネームの使用は終了となる場合でも、担当顧客からの問合せの可能性がある場合には、左記を想定した対応フローを定めます。 |
| 責任の所在 | 定められた手続きに基づいた適正使用については、所属長がその責任を有し、会社はその支援をするが、不正使用や規程外利用に対しては個人への懲戒処分となることなどを定めます。 |
| その他 | 関係法令や服す規程、その他必要なことなどを定義すます。 |
社外への共有の例
前述の通り、ビジネスネームを導入する際には、無用なトラブルを避けるため、予め社外に共有しておくことをお勧めします。
とはいえ、経緯を詳細に説明したり、お客様から了承をもらうような下手に出たりする必要はありません。ビジネスネームを導入すること自体は、お客様の利益や利便性を損ねるものではありません。そのため、導入の背景や目的について、以下のように簡潔に掲示しておけば十分です。
| WEBサイトまたは店頭案内などに以下のような文面を掲示する |
|---|
| 当社では今般、以下の目的のために、一部業務においてビジネスネーム(業務上使用する通称名)を導入いたします。 ビジネスネームの導入後は、これまで以上に良いサービスを提供し、お客様に喜んでいただけるよう努力して参りますので、何卒ご理解のうえ、変わらぬご愛顧を賜りますよう宜しくお願い致します。 【ビジネスネームの導入目的】 ・「従業員のカスハラ被害の防止」 ・「従業員のプライバシー保護」 ・「多様な働き方への配慮」 |
こういった掲示をすることで、無用なトラブルを避けられるだけでなく、採用活動においても、「この会社は従業員にしっかり配慮してくれているのだな」と思ってもらえ、プラスの効果を生む可能性もあります。
最後に|導入後のカスハラや顧客満足をチェックする
ビジネスネームの精度の導入は、導入したらそれで終わりという訳ではありません。むしろ、本当の課題は、継続的に改善し、制度を定着させ、導入目的を達成すること。そして更に、従業員満足度と顧客満足度の両立を図ることです。そのため、制度の導入後も定期的な振り返りと見直しを行い、運用をより良いものにして行きましょう。また、トラブル事例の検証も不可欠です。お客様対応において、ビジネスネームの導入新たに生じたトラブルがないかを確認し、規程やワークフロー、その他社内ルールに改善策反映をさせて行きましょう。
ビジネスネームの導入が原因で従業員の責任感やサービスレベルが低下したり、社外からの信頼を損ねたり、といった事態を避けるためには、自社に合った制度を設計するとともに、その制度が有効に機能するためのマネジメントシステム自体を作ることが重要です。
本コラムについて詳しくご相談を希望の方は、お気軽に下記からご連絡ください。