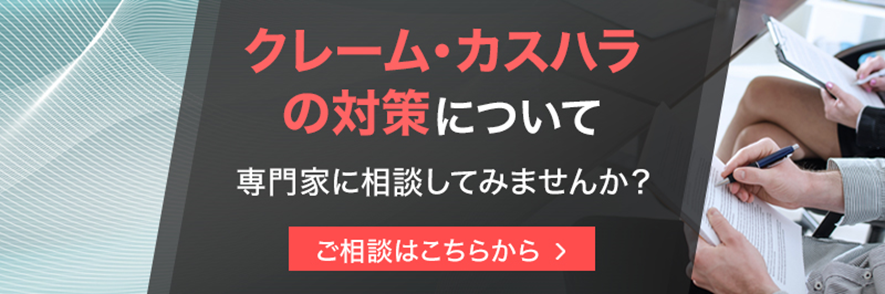それ、本当にカスハラ?|ISO10002によるカスハラ対策と顧客満足の両立

先日、ある手続きで市役所に行った時、隣のブースで、以下のようなやり取りがされていました。
- 職員:●●の手続きは、ちゃんと権利関係を証明できる書類を持って来ていただかなければ、お受けすることができないです。
- 訪庁者:「私は、●●の債権者で、裁判所の確定判決も持っています。ただ、事前に市役所のホームページで●●の解説を確認しましたが、「正当な権利を持っている人が対象」とは書いてあっても、「書類を持ってこい」とは書いていなかったので、持ってきていません。事前にちゃんと確認し、その通りに対応しているのに、書類を持って来なきゃダメと言われても困ります」
- 職員:いや、常識的に考えて、権利を持っているかどうかを確認するためには、書類が無ければ分からないじゃないですか。無いなら●●はできませんよ。
- 訪庁者:「それはあなたの常識でしょう。あなたは毎日●●をしているかもですが、こっちは分からないから事前にホームページをちゃんと確認して来ているんです。「無ければ分からない」と言うなら、そこにちゃんと書いておいてもらえれば、こちらは判決文を持って来ましたよ」
- 職員:そう言われても、書類が無ければこちらは確認できません。
- 訪庁者:「チッ、二度手間かよ。じゃあ、判決文持ってまた来れば良いんですか?」
- 職員:はい、この市に住んでいる方の●●なら、書類があればできます。
- 訪庁者:「え? 市外じゃダメなんですか? それも書いて無かったですよ?」
- 職位:ここは○○市なんだから、普通そうじゃないですか。無理難題ばかり言うなら、こちらもカスハラとして警察に通報しますよ!
訪庁者はその後も少し抗議していましたが、職員から少し強い口調で断られると、溜め息をつきながら帰って行きました。
問題は、その後です。
筆者が自分の手続きをしてもらっていたところ、訪庁者が帰った後の隣のブースで、後輩らしき女性に話しかけられたその職員が、「ああいうカスハラは、毅然とした態度で追い返さなきゃダメだよ」といったことを話していたのです。上記が真にカスハラであれば別かもしれませんが、その時の筆者の率直な感想としては、「これでもお客様が来てくれるのだから、羨ましい仕事だよな」と思わずにいれませんでした。
そこで本コラムでは、組織における苦情対応プロセスの適切な構築・運用のための国際規格であるISO10002(苦情対応マネジメントシステム)の枠組みに基づいて、カスハラ対策と顧客満足の両立を実現するための実践的な視点を、具体例を交えながら解説します。
それ、本当にカスハラ?|ISO10002によるカスハラ対策と顧客満足の両立
H2カスハラは深刻だが、排除には慎重であるべき
近年、カスタマーハラスメント(以下、カスハラ)は日本企業にとって深刻な社会問題となっています。少し前ですが、厚生労働省が2020年に行った調査によれば、顧客からの著しい迷惑行為(カスハラ)に該当する事案があったとする企業の割合は92.7%もあったとのことです。また、同調査では、「怒りや不満、不安などを感じた」は79.4%、「仕事に対する意欲が減退した」は57.1%の人が、「何度も繰り返し経験した」と回答しており、範囲だけでなく度合いについても深刻であることが分かります。
カスハラは絶対にダメです。しかし、それでも筆者は、相手をカスハラと決め付け排除することについては、企業として極めて慎重であるべきと考えます。理由は以下の通りです。
安易なカスハラ扱いのリスク
現場の従業員にとって、顧客からの厳しい叱責は精神的な負担になります。そのため「厳しい叱責=カスハラ」と短絡的に判断してしまうケースも少なくありません。しかし、安易にクレーマー扱いしてしまうと、正当な苦情や改善要求まで切り捨ててしまうリスクがあります。
例えば冒頭の例であれば、来庁者は事前に市役所のWEBサイトで解説を確認していたのに、窓口でその解説と違う理由で断られたことに不満を告げたところ、職員は自分の「常識」や「普通」を当てはめて来庁者をカスハラ扱いし、排撃してしまっているように見えました。これではサイトのユーザビリティを改善する機会を失い、同じ手続きをしようとした他の来庁者にまで不満が波及する恐れがあります。それでも代替の無い行政サービスなら、仕方なく言う通りに対応するかもしれませんが、競合のいる民間サービスでもお客様がまた来てくれるとは到底思えません。
雑音と改善機会の境界線
実は従業員にとっては、相手に怒られたりネガティブな指摘をされたりした時は、それを全部カスハラ扱いし排撃して良いなら、それが一番楽なのです。自分たちの落ち度を反省したり謝罪したりすることもなく、改善に伴う痛みを味わうこともなく、「カスハラだから追っ払ってやった」と言うだけで済ませられるなら、こんなに簡単なことはありません。
顧客からの苦情は、企業にとって「雑音」にも「改善資源」にもなり得ます。どちらにするかは、企業としての顧客対応に対する基本方針と、それを実現するための仕組み作りに次第です。
ISO10002には「クレーム」や「カスハラ」という言葉はありません。不満足の表明は「苦情」とし、「解決を期待しているもの」と定義しています。
例えば「WEBサイトの説明で、必要な書類が漏れていた」という苦情を解決し、より良いサービスを提供するための改善機会とするなら、必要な情報を追記するだけでなく、見やすく整理したり、動線を見直ししたりなど、無数の改善が可能になります。クレーマーやカスハラ扱いをすることで何の反省も改善もせず終わらせることに比べて、改善機会とすることでクレーム自体も減りますし、顧客満足の向上にも繋がります。
離反顧客を取り戻す困難さ
日経リサーチが2021年6月に公開した『クレームしない日本人、「痛点」に先回りし顧客離れ防ぐ』によると、不便や期待外れなどの痛点を感じた場合に、それを企業に申し出る日本人は27.5%に留まり、残り7割は、離反して行く場合でも企業に何も言ってくれないとなっていました。
また、マーケティングの世界では一般的に、新規顧客の獲得には既存顧客を維持することの5倍のコストがかかると言われています。当然、離反した顧客にも「1対5の法則」は当てはまりますが、不便や期待外れにより離反した顧客を取り戻すためにはそれら痛点の解消に要するコストも考慮する必要があるため、ますます困難度は高まります。
つまり、顧客が不満を表明した初期段階で、正当なクレームなのかカスハラなのかを正しく判断し、適切に対応ができなければ、売上やブランド価値を大きく損なうことになります。ISO10002の枠組みは、正当なクレームとカスハラを判断する枠組みを規程し、顧客の離反を防ぐ仕組みとしても活用が可能です。
ISO10002の枠組みと活用ポイント
ISO規格では、ISO9001(品質マネジメントシステム)の改訂に伴い、ISO10002も改訂されました。
ISO9001における大きなポイントは、トップマネジメントのリーダーシップ及びコミットメントが強調されたことであり、ISO10002にも反映されています。
苦情対応の基本原則におけるカスハラと顧客満足の両立(ISO10002:2018からの抜粋)
ISO10002には15の基本原則が定められていますが、その中でも以下の箇条が、カスハラ対策と顧客満足度の両立に密接に関わっていると考えます。
| 箇条番号 | 基本原則 | 解説 |
|---|---|---|
| 4.2 | コミットメント | 組織は、苦情対応プロセスを定め、実施することを、積極的にコミットメントすることが望ましい。 →対応方針やプロセスについて、トップマネジメントが、社内外に対し明確に表明すること。 |
| 4.7 | 客観性 | 苦情はそれぞれ、苦情対応プロセス全体を通じて、公平で、客観的かつ偏見のない態度で対応することが望ましい。 →現場の恣意的運用や顧客の態度に左右されず、統一した基準により客観的に判断すること。 |
| 4.11 | 顧客重視のアプローチ | 組織は、苦情対応に関する顧客重視のアプローチを適用し、フィードバックを積極的に受入れることが望ましい。 →正当な苦情には、商品・サービスの品質を向上させ、顧客満足度を高めるために組織全体で活用する。 |
カスハラの判断基準を具体化し、それに基づいたマネジメントシステムを構築する
苦情を強い言葉で伝える顧客の中には、企業に期待しているケースも多くあります。しかし、企業側は声の大きさに惑わされず、要望の中身を冷静に分析し、自社の商品やサービスの改善に活かして行くことが不可欠です。
冒頭の例であれば、例え強い口調やしつこい態度と感じられたとしても(筆者にはそうは感じませんでしたが)、来庁者の「二度手間は避けたい」「必要な書類はちゃんと書いておいて欲しい」などの苦情は、ごく当然のものです。そのような当然の苦情をクレーマーやカスハラとして扱ってしまえば、改善の機会を失うばかりか、顧客満足度を大きく低下させることに繋がります。
このような改善機会を失わないようにするためには、まず、カスハラの判断基準を具体化する必要があります。自社にとってのカスハラはどういった行為か、どのような方針、基準、観点で判断するのか、といったことを明確にし、組織として統一的な判断を可能にすることが重要です。
この時、カスハラの定義に沿った顧客対応方針の確立から、それに基づいたマネジメントシステムを構築し、マニュアルや従業員教育まで落とし込んで行くために、ISO10002の枠組みは非常に有効です。ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)と同様に、多くの業界や団体で確立された苦情対応マネジメントシステムの枠組みを使って、「毅然と拒絶すべきカスハラ」と「顧客満足につなげる正当なクレーム」を定義し、組織的な対策を構築して行きます。
【カスハラとは?】事例に基づいた具体的な基準と、対応のポイントを解説
「カスハラには毅然と対応する」といったスローガンだけで、組織的な仕組みや経営の関与がそれに伴っていなければ、改善意見とカスハラの区別もつかず不満や苦情を全て排撃してしまい、顧客満足の大幅に低下させることになりかねません。
そのため当社では、いわゆる基本方針やガイドラインを策定する際は、ISO10002の枠組みなどを活用し、それに伴う社内のマネジメントや教育などの制度を整備することを、強くお勧めしています。
本コラムの内容について、もう少し詳しく話しを聴いてみたいという方は、お気軽に下記からご連絡ください。
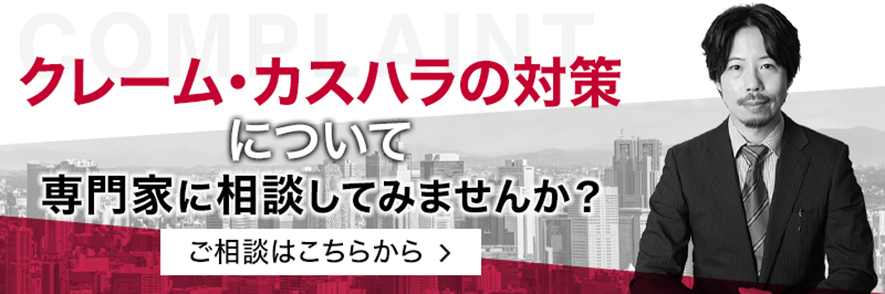
カスハラ対策と顧客満足度を両立させる5つのポイント
世の中には暴力や不当要求、人格否定などの伴うカスハラもあり、従業員にとってそういったカスハラは深刻な問題です。ですから、一度でも経験したり、または周囲で該当する話しを聴いたりしたら、ついそれに引っ張られて、排撃一辺倒の対応をしてしまいがちです。
しかし、企業にとってお客様は、自社に売上を与えてくれる唯一人の存在です。そのお客様を簡単に排撃するような仕組みや文化を作ってしまえば、顧客満足を大切にする価値観を醸成するのは、並大抵の苦労では不可能です。そのため、対策の初期段階から、自社の顧客対応の在るべき姿を踏まえた上で、カスハラ対策と顧客満足度向上の両方に取り組むことが重要です。
以下、取り組みのポイントを解説します。
「カスハラ対策方針」ではなく、カスハラ対策と顧客満足を包含した「顧客対応基本方針」を策定する
カスハラ対策をガイドラインとして明文化することは、現場の従業員を守るうえで大きな意味を持ちます。しかしそのガイドラインが「カスハラ対策ありき」では、顧客満足の視点を欠いてしまい、かえって企業にリスクをもたらすことになりかねません。冒頭の例のように、顧客の正当なクレームまで封じ込めるような対応がガイドラインの曖昧さに起因しているのであれば、それは大きな不備と言えます。
カスハラ対策だけが目的となり、不要な排撃を招かないように、自社の顧客対応の在るべき姿に基づき、カスハラ対策と顧客満足を包含する基本方針(ガイドライン)を作成しましょう。
カスハラ対策ガイドライン(基本方針)作成の5ステップを具体的に解説
実効性を担保するための社内制度(マネジメントシステム)を設計する
仮に、冒頭の例が、その職員が逸脱していただけでガイドライン自体は適正だったとしても、事後に談笑していた同僚職員が当たり前の様に「カスハラ扱いによる改善機会の放棄」を受け入れていたことを考えると、組織内に浸透させるようなマネジメントシステムや教育は全くできていなかったと推測できます。そのような不完全な状態では、今回は改善機会の放棄でしたが、本当にカスハラであったとしても、適切に対応できていたかは疑問です。
基本方針(ガイドライン)の実効性を担保するため、どのようなルールに基づいて、誰が、いつ、何をするか、誰がモニタリングし、誰がコントロールするのかといった、具体的なマネジメントシステムを設計しましょう。
マニュアル、研修、評価基準などに反映させる
策定したガイドラインは、単なる文書で終わらせず、現場で実際に活用できる形に落とし込む必要があります。具体的には、
- 対応マニュアルの整備
- 研修プログラムへの組み込み
- 人事評価基準への反映
といった仕組みが重要です。例えば、単に「毅然と対応した」ことを評価するのではなく、何に対して、なぜ、どのように対応したのかなどと掘り下げながら、クレームやカスハラと顧客満足度向上の両面から評価をすることが、現場への正しいメッセージになります。
経営による継続的なモニタリングを実施する
ガイドライン、マネジメントシステム、対応マニュアルなどを整備したからと言って、カスハラ対策を現場に丸投げすることは絶対に避けなければなりません。経営層が定期的に苦情対応の実例をモニタリングし、組織としての在るべき顧客対応の姿に向かうように継続的にフィードバックすることで、カスハラ対策と顧客満足度向上の両立に近づけます。経営が関与し続けることにより、現場には「自分たちだけに責任を押し付けられているのではない」という安心感が生まれるとともに、カスハラ扱いして終わらせず改善機会としなければならないという緊張感も生まれ、組織全体で一貫性を持った対応が可能です。
ISO10002でも、経営のコミットメントは重視しており、プロセスの適否を評価する内部監査や、経営に対する定期的なマネジメントレビューを必須としています。
クレーム・カスハラの対策共有会議 「振り返り」の5つのポイント
カスハラ対策と顧客満足度向上を共に大切にする組織文化を醸成する
カスハラ対策に偏重すると、顧客満足を軽視した組織風土が生まれるリスクがあります。そのため経営層は「顧客満足は企業の持続的成長に不可欠である」というメッセージを繰り返し発信する必要があります。年頭訓示、経営計画の発表時、会議の冒頭、朝夕礼、社内報など、様々な場を通じて伝えて行きましょう。営業所が地理的に離れていたり、24時間営業であったりする場合は、経営から直接メッセージを伝えるのが難しいこともあります。しかしそういった場合も、オンラインにしたり、動画メッセージを送ったりするなど、工夫次第で伝えることはできます。
また、カスハラ対策も顧客満足度向上も、一過性の施策ではなく組織文化に定着させなければ効果が持続しません。例えば、定期的な振り返り会議で「成功した顧客対応事例」としてカスハラ対応とお客様に喜んでもらえた事例の両方を共有し、従業員同士で学び合う仕組みを構築することが有効です。こうした活動が、従業員保護と顧客満足の両立を「組織の当たり前」の組織文化として根付かせます。
まとめ:企業にとっては、カスハラと顧客満足を俯瞰した対策が重要
今回解説して来た通り、カスハラ対策は、適切な仕組みを構築できないと正当な顧客の声まで封じてしまい、顧客満足度の大幅な低下につながるなど、かえって企業にリスクをもたらしかねません。そのため当社では、特に対策の初期段階においては、専門家の知見を取り入れることで、より実態に即した形で、カスハラ対策と顧客満足度向上を俯瞰した対策をして行くことがお勧めしています。
当社は、部下の分も合わせると3,000件以上のクレームに対応して来た元・コールセンターの品質管理チームマネージャーであり、カスハラ対策と顧客満足向上の専門家であり、ISO10002のご支援も可能です。
本コラムの内容について無料相談を希望の方は、お気軽にご相談ください。