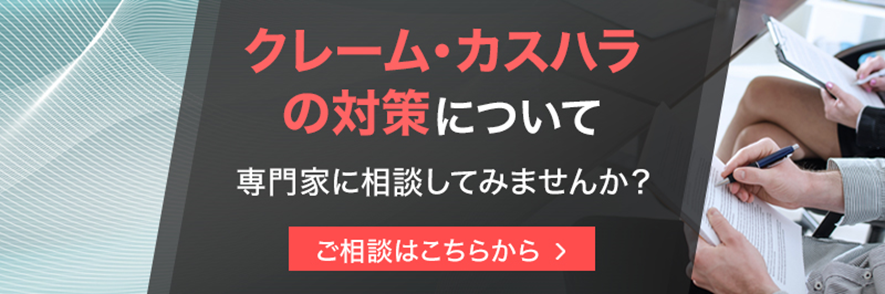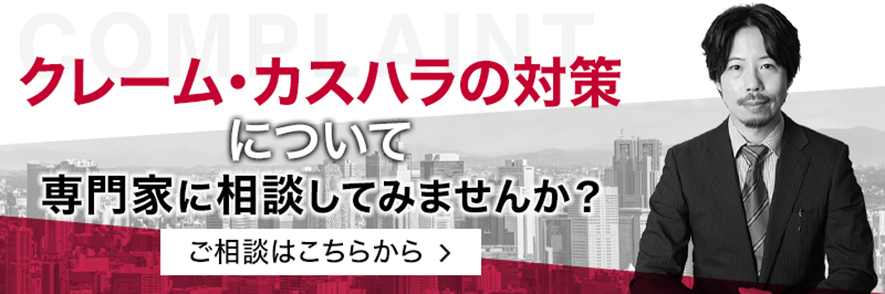【保存版】クレームで「上司を出せ!」「社長を出せ!」と言われた時の対応

「上司を出せ」「社長を出せ!」といった要求は、悪質クレームやカスタマーハラスメント(カスハラ)の常套句です。
こういった要求に安易に応じてしまうと、以下のような問題点が生じます。
- 部下の責任感が低下し、サービスの品質が低下してしまう
- 上司の本来業務が滞ってしまうため、部署全体の生産性が低下する
- 上司に改めて説明させることになるため、顧客満足度が低下する
- クレーマーに「ゴリ押しすれば通る」と学習され、次のクレームやカスハラに繋がる
一方、上司への交代要求の中には、担当者の不適切な言動に起因したものなど、客観的に見て上司に交代するのが妥当と思われるケースもあり、闇雲に交代を拒絶するだけでは顧客満足度を低下になります。
従業員満足の視点でも、適切な支援が無いまま従業員に押し付けてしまえば、最悪の場合、従業員満足度から退職や悪評の蔓延に繋がることもありえます。
このように、「上司を出せ!」「社長を出せ!」といった要求への対応は、企業、顧客、従業員という3者の立場に配慮する必要があり、拒絶して終わりといった、簡単なものではありません。
こうした背景からも、個人のスキルに任せるのではなく、組織として明確な対応ルールと体制を整えることが不可欠です。
本コラムでは、「上司を出せ!」「社長を出せ!」といった要求に対して、現場でどのように対応すべきかを具体的に解説していきます。
【保存版】クレームで「上司を出せ!」「社長を出せ!」と言われた時の対応
なぜ「上司を出せ」「社長を出せ」が起こるのか
「上司を出せ」「社長を出せ」といった要求は、単なる感情の爆発だけでなく、背景にはさまざまな要因が潜んでいます。
現場での対応力を高めるためには、まずは、なぜこうした理不尽な要求が起こるのかを理解しておくことが重要です。
例えば、東洋大学の社会学部長であり、犯罪プロファイリングの専門家でもある桐生正幸教授は、著書『カスハラの犯罪心理学』の中で、暴力犯罪の動機として「回避・防衛」、「影響・強制」、「制裁・報復」、「同一性・自己呈示」の4タイプを挙げています。
| 暴力犯罪の動機 | パーソナリティ |
|---|---|
| ①回避・防衛 | 猜疑心、非差別感 →「自分が危害を加えられている」「私が危ない目に遭ったのは、あいつの悪意のせいだ」「私が損をしたのは、あいつの敵意のせいだ」といった被害意識から攻撃行動を高める。 |
| ②影響・強制 | 競争心、自己主張、支配性、低言語スキル、低対処スキル →自分の意見を通すために戦略的に攻撃行動を使う。 |
| ③制裁・報復 | 信念の偏り、報復心、権威主義 →「自分が正義」「責任は相手にある」と信じる傾向が強い人がとる攻撃タイプ。 |
| ④同一性・自己呈示 | 男らしさ、対抗同一性、自己顕示性、プライド →対面やプライドへのこだわりが強い人、たくさん注目されたい人がとる攻撃タイプ。 |
(『カスハラの犯罪心理学』より本サイトで作図)
顧客の要求の背景には複数の要因が重なっていることが多く、上記の他にも、ストレス発散、受ける側との相性、癖などの様々な要素が絡んでいます。
しかし、「上司を出せ」「社長を出せ」と主張する背景を把握できれば、感情に振り回されず適切な対応ができます。
現場対応者が「なぜこの要求が出たのか」に意識を向けることで、過剰な譲歩や感情的なやり取りを避け、組織としての信頼性や一貫性のある対応へとつなげられます。
上司に代わるべきかの判断軸
前述の通り、「上司を出せ!」「社長を出せ!」といった要求には慎重な判断が求められますが、原則として、安易に上司へ交代すべきではありません。
理由は、たとえ自社側にミスがあったとしても、上司や社長が関与していない限り、それらの存在に交代する合理的な理由はなく、問題解決に直結しないからです。
ただし、上記に交代しないことは、絶対のルールという訳ではありません。
例えば、下記のような状況などにおいては、柔軟に上司への交代を検討しましょう。
- 上司が直接関与している、または原因になっている場合
- 上司が専門知識を持ち、早期対応が損害軽減につながる場合
- 組織としての責任を示す必要がある場合
- 現場スタッフの業務知識やスキルが未熟で対応の継続が困難な場合
- 現場スタッフが恐怖やストレスで対応の継続が困難な場合
- お客様のお体や財産に損害が発生している可能性がある場合
なお、上記に当てはまる場合でも、組織的な防衛の仕組みや従業員に対する適切な教育を行うことで、上司への交代を減らして行く努力が重要です。
謝罪の鉄則:内容に応じた適切な立場の者が行うべき理由
謝罪の大原則は「ミスに応じた立場の者が謝罪をすること」です。
お客様が納得するかどうかは感情の問題であり、気持ちの問題である以上、企業側が完全にコントロールできるものではありません。
コントロールできない以上、お客様に納得していただけるように誠実に対応することは重要ですが、従業員やスタッフのミス、不適切な言動に対して、上司や社長がその都度謝罪をして回る必要はありません。
企業は、全ての業務を社長が直接指揮しているわけではありません。
部長、課長、主任、担当者といった階層で役割や権限を分担し、方針やルールに基づいて仕事をしています。
ですから、重大な不祥事や組織的な欠陥の場合などを除き、業務上のクレームに対しては、まず、それをしてしまった本人が真摯に謝罪を行うべきです。
そして、上司からの謝罪が必要な場合であっても、担当者を指導する立場である一階層上の上司までで十分です。
担当者やその直属の上司が真摯に謝罪したのにもかかわらず、なお執拗に上層部への交代を求めて来たり、謝罪に乗じて無理な要求をゴリ押しして来たりする場合は、毅然とした態度でお断りしましょう。
一方、謝罪すべき場面で本人やその上司が責任を回避しようとすると、企業としての姿勢が問われ、更に上層部への交代を要求される理由になりかねないため、注意が必要です。
従業員・スタッフを守るための組織的なカスハラ対策
「上司に代われ!」「社長を出せ!」と強く要求される場面では、多くの場合、対応が長引き、激怒や長時間対応といった負担が発生します。
お客様にとっては企業側のミスに起因した正当なクレームであっても、従業員にとっては、長時間のクレーム対応は大きなプレッシャーです。
ましてや、悪質なハードクレームやカスハラの場合には、従業員やスタッフのストレスはさらに深刻になります。
そういったプレッシャーやストレスから従業員を守るためには、「上司に交代しろ!」「社長を出せ!」といった要求に対するカウンタートークの準備や、感情的なやり取りを回避する仕組み作りなど、組織的な対策が必要です。
カスハラは、個人のスキルや判断力だけでは対処しきれない場面も多いです。そのため、現場任せにせず組織的な対策を整備することは、従業員の安心と企業の信頼にも直結します。
具体的なカスハラ対策(「上司を出せ!」「社長を出せ!」に備える)
カスハラが発生する場面は、対面・電話のどちらでも発生します。現場スタッフが過度な負担を感じずに対応できるよう、環境面や運用面の備えを組織的に整えておくことが重要です。
感情的な要求がエスカレートしやすい場面では、抑止力のある仕組みやルールの可視化が有効です。
以下は、窓口・電話対応の現場で実施できる対策例です。
窓口対応の場合
- 自社のカスハラ対応指針や、国のカスハラ対策ポスターをお客様の目につく場所に掲示する
- 威圧的な言動を抑止するため、監視カメラを設置する
- 一人で対応せず、複数名(できればお客様と同等以上の人数で)対応する
電話対応の場合
- 録音システムを導入し、録音アナウンスを事前に伝える(例:サービス品質向上のため)
- WEBサイトやパンフレットの問合せ先電話番号の近くに、ガイドラインの抜粋を掲載する
- 非通知拒否や、頻繁な場合には着信拒否を設定する
事前対策の重要性
事前の対策を徹底することで、従業員の精神的負担を和らげ、組織としての対応力も高まります。
また、担当者が一貫して対応することで、交代により最初から説明し直さなくても良いので、対応がスムーズになります。
「上司を出せ」「社長に代われ」というクレームは、常套句ではありますが、その場しのぎの対応では現場も企業も守れません。
誰が対応しても一定の対応ができる仕組みや体制作りが、企業全体のリスクを減らし従業員を守る手段になります。
当社では、カスハラ対応に関するガイドラインの作成やマニュアルの整備、従業員への教育研修、モニタリングなど、様々なクレーム・カスハラへの対応についてご相談を承っております。
「対応に不安がある」「仕組みを整えたい」と感じた企業様は、ぜひ一度ご相談ください。
【事例で解説】上司への交代要求にどう対応するのか
ここからは、事例に基づいて、実際のクレーム対応の流れとともに対処のポイントを見ていきましょう。
設定は一部変更していますが、「些細なミスに付け込み執拗な謝罪と過剰な要求を行い、要求が通らないと上層部への交代を求めてくる」といった事例は、筆者自身が実際に経験したクレームです。
商品交換ができず「上司を出せ」と要求された場合
商品の交換対応を断ったことで、お客様が激昂し「店長を出せ」と要求されたケースです。お客様が感情的になって来たとしても、冷静に対応することが重要です。
【やり取り①】説明不足による初期のトラブル発生
- お客様:「お前、事情も聴かないでいきなり断るってどういうことだよ!?」
- 従業員:「申し訳ありません、ちゃんと拝聴してから回答すべきでした。」
- お客様:「で、どうなの?事情ちゃんと教えたんだから、交換してくるんだよな?」
- 従業員:「申し訳ございません、まずはレシートを確認させていただけますでしょうか」
【やり取り②】説明が伝わらず、上司交代を要求される
- お客様:「いきなり断っておいて、今度はレシート出せってどういうことだよ?」
- 従業員:「他のお店でも売っている流通品ですから、最低限、当店でご購入いただいたことを確認のうえで対応しております。」
- お客様:「俺が嘘つきだっつーのか?おめぇーじゃ話しになんねぇーから店長に代われよ」
【やり取り③】真摯に謝罪し、自分が対応することを伝える
- 従業員:「私の言動が不愉快に感じられたのであれば、私が謝罪いたします。大変申し訳ありませんでした。」
- お客様:「いいから店長に代われよ」
- 従業員:「お客様への対応は我々スタッフが担当することになっております。上司には私が責任を持って報告し、指導を受けますが、お客様への交代はいたしかねます。」
- お客様:「店長に代われって言う客の希望がきけねぇーのか!?」
- 従業員:「申し訳ありません。」
【やり取り④】代替案を提示し、話題をご不満の解消に戻す
- お客様:「ならさっさと交換しろよ。お前が事情も聴かないでいきなり断って来たせいで余計な時間くってイラついてんだよ。“ 責任を持つ “ っつーなら交換しろよ!」
- 従業員:「事情も聴かずお断りしたことは、私の対応ミスでした。その件は改めてお詫び申し上げます。しかし、交換に応じられないと申している訳ではなく、購入履歴さえお示しいただければ対応可能です。レシートを破棄されたのであれば、クレジットカードの利用明細などご確認してみていただけないでしょうか。」
【やり取り⑤】再度の交代要求に対し対応継続を伝える
- お客様:「面倒臭ぇーな、いいから店長に代われよ」
- 従業員:「恐れ入りますが、必要な謝罪と提案はしております。私が本件の担当者なので、私が最後まで責任を持って対応いたします」
ポイントは、ミスと要求を分けて対応すること
上司への交代をお断りするうえで重要なのは、「是々非々で対応する姿勢」を徹底することであり、以下の3ステップで対応するのが有効です。
- ミスと“それ以外”とを明確に分ける
- ミスに応じた謝罪を速やかに行う
- “それ以外”の部分について、組織としてのルールや方針に沿った解決策を提示する
感情や勢いに流されずに、謝るべきことには真摯に謝罪し、そうでないことには冷静な説明と代替案を提示することで、従業員を守りつつ毅然とした対応が可能になります。
また、ミスに応じた適切な謝罪と建設的な提案がスムーズに行えることは顧客満足度の向上につながり、一貫した姿勢は、企業としての信頼感や誠実さを伝えることにもつながります。
「上司に代わっても同じです」は逆効果になる理由
時折、「上司に代わっても対応は変わりません」といったトークを耳にしますが、この表現は推奨できません。
なぜなら、断定的で上から目線の印象を与える恐れがあり、「なぜ上司では無いお前が“変わらない”と決めつけるんだ!?」と、新たな不満を引き起こす可能性があるためです。
対応時には、上記例のように、上司への交代に応じられない理由を会社の方針であると伝えたうえで、担当者自身が責任を持って対応すると説明することが望ましい対応です。
属人的な対応は危険!クレームやカスハラへの対策は組織で行う
本コラムでご紹介したような対応をすることで、「上司を出せ!」「社長を出せ!」と言われても、交代せず担当者がそのまま対応できることが多くなるかもしれません。
しかし、それだけでは根本的な解決にはなりません。
もしそれがその担当者だけの属人的な対応なら、他の担当者を突破されてしまい、最悪の場合、「なんであいつは上司を出さなかったんだ!?」と二次クレームになりかねません。
それでは、企業にとってはリスクそのものですし、従業員にとっては不安そのものです。
また、属人的な対応に委ねていると、お客様のお体や財産に損害が発生している可能性があるなど、速やかに上司に交代すべき案件まで拒絶してしまったりする可能性もあります。
「上司を出せ!」「社長を出せ!」といったクレームに適切に対応するためには、誰もが同じように対応できるようにするための、組織的な対策が不可欠です。
【まとめ】誰でも対応できる現場へ|まずは無料相談をご活用ください
「上司に代われ!」「社長を出せ!」とう言葉は、クレームやカスハラの常套句です。
筆者自身も、勤務時代は何十回も言われて上司に交代し、その後は、上司として対応して来ました。
その経験を通じて強く感じるのは、典型的な事例であるからこそ組織としての対応方針や組織的な対策が有効だということです。
「よくあることだから」と現場任せにしていたら、今までそうだったように、この先もずっとこの典型的なクレームが減ることは無いでしょう。
しかし、常套句であるからこそ、誰でも対応できる再現可能な対応の仕組みを作れば、迎撃できるだけでなく、「上司に代われ!」「社長を出せ!」と言われること自体を減らせる可能性もあります。
こういったクレームの根本解決ができれば、従業員が安心して働けるようになるだけでなく、上司・マネージャーも本来業務に集中できるようになるので、職場の生産性自体の向上に繋がります。
早急な対策への着手を、強くお勧めします。
専門家に無料相談をご希望の方は、お気軽に下記からご連絡下さい。